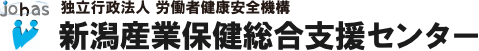【重要】産業保健関係助成金に関する重要なお知らせ(令和4年11月9日公表)
出典:独立行政法人労働者健康安全機構サイト
※内容を抜粋して記事を作成しています。
令和4年11月9日公表
当機構本部より、産業保健関係助成金につきまして重要なお知らせです。
詳しくはこちらをご参照ください。
「THP指導者研修会(オンラインによるレベルアップ研修会)」のご案内~働く人の認知症予防~ ほか (新潟THP推進協議会)
新潟県THP推進協議会では、年2回レベルアップ研修会を開催しています。
オンラインによる研修会です。全国どちらからでも、ご参加可能です。
職場での健康づくりを推進される皆様方は勿論、参加者ご自身の健康づくりにも、お役に立てていただけるものと思います。皆様のご参加をお待ちしております。
■ 開催日時 2022年 12 月 16 日(金)13:00~16:20
■ 参加費 新潟県THP推進協議会会員:5000円(税込) 非会員:7000円(税込)
■ 詳細はこちら → THP指導者研修会(オンライン)のご案内
新潟労働局より、最新の労働衛生行政の動向についてご講演いただくほか、筑波大学大学院教授の山田実様より「フレイル」について、新潟大学教授の池内健様より「若年性認知症」などについて、予防等を含めてご講演をいただきます。
■申込先はこちら→THP指導者(オンライン)研修会申込フォーム
※本研修会は、THP指導者登録更新のためのレベルアップ研修として2単位取得可能です。
■お問い合わせ先
新潟県THP推進協議会 事務局(鈴木・宗村)
TEL:025-370-1945 メール:kenkousuisin@niwell.or.jp
新潟産業保健総合支援センター及び各地域産業保健センターをご利用の皆様へ
当センターでは産業保健に関するセミナー研修、メンタルヘルス対策支援、治療と仕事の両立支援など、地域産業保健センターでは労働者50人未満の小規模事業場に対し、労働安全衛生法に定められた健康診断結果に基づく医師からの意見聴取、保健指導などの産業保健サービスを無料で提供しております。これらのサービスは、国からの補助金により提供されておりますが、活動資金には限りがあり、状況によってはお申込みをお受けできない場合もあります。
ご利用の皆様には、ご不便をおかけいたしますが、ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
出典:新潟労働局
※内容を抜粋して記事を作成しています。
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。
過重労働による健康障害等を防止するためにも、職場で労働時間が適正に把握されているか確認しましょう。
時間外・休日労働時間が労使協定の範囲内で適切に運用されているか確認しましょう。
また、過労死等防止について県民の啓発を図ることを目的として、令和4年11月30日に「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します。
労働相談、またはご不明な点等がございましたら、以下までお問い合わせください。
≪問い合わせ先≫
新潟労働局労働基準部監督課
TEL:025(288)3503
厚生労働省ホームページ:11月は「過労死等防止啓発月間」です
リーフレット「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について」
過労死等防止対策推進シンポジウム
【女性労働協会】「母性健康管理指導事項連絡カード(母性連絡カード)が改正され新しくなりました!」
「母健連絡カード」とは、事業主が、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置 を適切に講じるために、医師や助産師の指導事項の内容を事業主に的確に伝達するカー ドです。男女雇用機会均等法に基づく指針において様式が定められており、医師等による証明書となるものです。 「母健連絡カード」の新様式は、令和3年7月1日から適用されます。
詳しくは、以下をご覧ください。
【厚生労働省】依存症について正しい知識と理解を持ち、当事者の方を早めに治療・支援につなげましょう
出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。
アルコールや薬物、ギャンブルなどを“一度始めると自分の意思ではやめられない”、“毎回、やめようと思っているのに、気が付けばやり続けてしまう”-それは「依存症」という「病気」かもしれません。
一般的なイメージでは、“本人の心が弱いから”依存症になったんだ、と思われがちですが、依存症の発症はドーパミンという脳内にある快楽物質が重要な役割を担っています。アルコールや薬物、ギャンブルなどの物質や行動によって快楽が得られます。そして、物質や行動が繰り返されるうちに脳がその刺激に慣れてしまい、より強い刺激を求めるようになります。その結果、物質や行動がコントロールできなくなってしまう病気なのです。
また、依存症は「孤独の病気」とも言われています。例えば「学校や職場、家庭などとうまくなじめない」といった孤独感や「常にプレッシャーを感じて生きている」「自分に自信が持てない」などの不安や焦りからアルコールや薬物、ギャンブルなどに頼るようになってしまい、そこから依存症が始まる場合もあります。
さらに、依存症は「否認の病気」とも言われており、「自ら問題を認めない」ため、本人が病気と認識することは困難です。一方、家族はアルコールによる暴力やギャンブルによる借金の尻ぬぐいになどに翻弄され、本人以上に疲弊するケースが多くみられます。
「(家族や知人が)依存症かもしれない」そう思ったら、1人で抱えこまず、また1人で解決しようとせずに、まずは、お近くの保健所や精神保健福祉センターにご相談ください。
家族や友人など周りの人が、依存症について正しい知識と理解を持ち、当事者の方を早めに治療や支援につなげていくこと。それが依存症を予防し、また回復につなげる大事な一歩です。
【相談機関】
1)保健所
新潟県内の保健所の一覧はこちら
2)精神保健福祉センター
新潟県精神保健福祉センター
〒950-0994 新潟市中央区上所2-2-3
TEL: 025-280-0111 FAX: 025-280-0112
相談電話(専用): 025-280-0113
新潟市こころの健康センター
〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1
TEL: 025-232-5551 FAX: 025-232-5568
相談電話(専用): 025-232-5560
3)自助グループ
身近な居住地に利用したい自助グループ・回復支援施設があるかどうか等の情報は、保健所または精神保健福祉センターにお問い合わせください。
【リンク】
さらに詳しい情報は厚生労働省HP及びリーフレットでご確認ください。
依存症対策ページ(厚生労働省)
リーフレット「わかっているのにやめられない~それって依存症かも~」(pdf)(厚生労働省)
出典:厚生労働省HP
※内容を抜粋して記事を作成しています。
厚生労働省は、労働安全衛生法に基づく健康診断の実施、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の措置の実施について、事業者の皆様に改めて徹底していただくことを促すため、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的に啓発を行っています。
事業者の皆様におかれましては、健康診断の実施状況等をご確認いただき、適切な実施にご協力くださいますようお願いします。
詳細は以下をご覧ください。